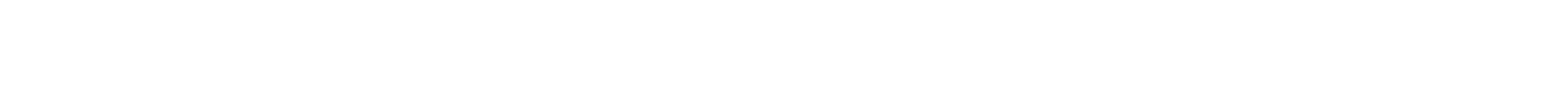SM、サド・マゾの言葉の語源が作家の名前から採られいることは多くの人が知ってますよね。
実際にマルキ・ド・サドの小説を何点かと伝記を読んだことはあるのですが、ザッヘル・マゾッホは読んだことなかったなぁと思い当り、有名な小説「毛皮を着たヴィーナス」を読んでみました。
どんな知らない世界を知ることになるのかな・・・。
目次
あらすじは・・・

カルパチア山脈の保養地で青年ゼヴェリーンは、未亡人の美女ワンダ・フォン・ドゥナーエフと出会います。
二人は互いに好意を持つものの、ワンダは「異端の魔女より始末に悪い女、異教徒」と自らを呼び、世間一般の価値観や制度に従う気はさらさらないようです。
ワンダのそばを常に離れたくないくらい好きになってしまったゼヴェリーンは、結婚をしてくれないのであれば、自分をあなたの奴隷にしてずっと側に置いて下さいと懇願するのです。
こうして二人は、貴婦人とその奴隷としてイタリア・フィレンツェへ旅に出ます。
ゼヴェリーンの奴隷生活は旅の行程から始まります。
足蹴にされ、想定を超えた命令や仕打ちにショックを受けながらも、美しい女に跪いたり、鞭で打たれることに無常の喜び、本人の言うところの肉欲を超越した世界”超官能”を感じるのでした。
こうしてワンダと奴隷契約書を交わすのでした。
愛している男が求めるような”女主人”として振る舞うワンダと奴隷でいたいゼヴェリーンの関係に、傲慢な一人のギリシャ人の男が登場するのです。
ワンダはそのギリシャ人の男が気になって仕方がない様で、ゼヴェリーンにとっては嫉妬をもたらす苦痛であり、その苦痛さえもゼヴェリーンにとっては”超官能”的劣情を禁じ得ない様です。
最後にゼヴェリーンはワンダから手酷い裏切りにあい、ワンダはギリシャ人の男と共にゼヴェリーンのもとを去って行きます。
もしかしてマゾな人って、実はワガママな性格?

エロティシズム、フェチシズムな世界を色々観てみたいと思っていても、拷問など「苦痛系」は好みではないなぁ、とサドの作品を読んだとき改めて認識した次第です。
サドの作品に登場する悪徳な者たちは一方的な淫蕩と拷問の果てに命を奪います。
それを「自然が望んだこと」と曰います。
「毛皮を着たヴィーナス」ではゼヴェリーンが鞭打たれ血を滴らせるシーンが描写されるのですが、
ゼヴェリーンは崇拝するワンダに対して自ら隷属を望み、残酷な仕打ちを懇願するので、ある意味拷問者と被害者が合意の上での行為ということになるのでしょうか。
その上ゼヴェリーンは殺されることはないですから。あなた様の手にこの奴隷奴の殺生与奪の権利を献上しますくらいは言ってましたけど。
奴隷として過酷な扱いをされ、鞭で打たれてから、女主人に優しく包まれキスをされる、まさにアメと鞭。
そんな時のゼヴェリーンが本当にこれ以上ないくらい幸せな気持ちに包まれいるのが文章から伝わってくる気がします。
(因みに、そういえばこのお話に、全裸やセックスするシーンは無かった様な・・・。)
でも思うに、ゼヴェリーンは我儘なのかな?
お互いに惹かれ合っている二人なのですが、一般の常識や道徳観念に縛られたくないワンダは結婚をするつもりはなく、それならばあなたの奴隷にしてくださいと執拗に一方的に懇願するゼヴェリーンに対しては困惑します。
お前の側に居たい、妻になってくれないなら俺を奴隷として側に置け!。
俺の望む通りのご主人様になれ!。
俺を責める時は毛皮を纏ってくれなければ駄目だ!。
俺の内に秘めた”超官能”に貢献してくれ!。
と一方的に迫っている様にも見えます。
ワンダは一度は拒み、説得をします。奴隷にしろと言われる度に本当にそれを望むのか訊ね、戸惑います。
その問いと戸惑いは奴隷契約書にゼヴェリーンがサインした後にもあるのです。
聞く耳を持つつもりがなさそうなゼヴェリーンに根負けしてか了承するのですが、話を聞いているうちに自分の内にも魔性の部分にあることに時々気付いてくる様な描写もあったりします。
面白いのは、ワンダが自分の想像を超えた行為に出るとゼヴェリーンは戸惑ったり戦慄を覚えたりして激しく慄いたりすのですけどね。
こうして愛したパートナーを自分が望む女へと導いていく。
この物語もギリシャ神話のピグマリオン物語の系譜なのでしょうか?
でも最後はワンダに愛想を尽かされてしまうのでしょうか。
ワンダは”ギリシャ人”と結託してゼヴェリーンを裏切り捨てて行くのです。
責められたいと強く願うことは病気?

アムステルダム国立美術館
正直な気持ちとしてこの物語の結末をどう解釈していいのか困っています。
ワンダにとってのゼヴェリーンは、出逢った時こそ”風変わりな可愛い人”でそんな”男の子”に結婚したいくらい好きだと告られれば退屈しのぎの相思相愛も有り、だったのでしょうか。
でも彼女は最初から自分は結婚はしない、するのであれば心身を支配されても構わないくらいの強い男でなければダメと言ってますね。
それがワンダにとっての”ギリシャ人”の男ということでしょうね。
ゼヴェリーンと付き合うのも夫婦としてやっていけるかのお試しとも言ってましたでしょう。
頑なに「俺の望むように女王様として振る舞って自分を奴隷にしろ!」と迫ってくる男とはきっと一緒にはなれないと早い段階で考えていたのでしょう。
だから自分好みの男が現れちゃったし面倒な貴方とはサヨナラです、ってことですよね。
この面倒な男と後腐れなく別れるにはあのような残虐な荒療治しかなかったのかな。
後年ワンダはゼヴェリーンに宛てた手紙で、”健やかな精神を芽生えさせるための必須の治療”をしてあげたのよ、なんて言ってますね。
貴方への愛の置き土産よ、みたいな取って付けた言い訳のようにも聞こえますが、ゼヴェリーンにとっては効果があったのでしょう。
残虐な荒療治はゼヴェリーンの内なる”超官能”の世界を粉微塵に粉砕してしまったように見えますけど。
ワンダに捨てられたゼヴェリーンは故郷に帰り、父の跡を継ぐための教えを受け労働に従事して農場主(貴族にして地主という身の上)となるのです。
汗を流し、義務を果たし分別のある日々を過ごす自身を”健康”になったと言います。
”超官能”の世界を望んだあの頃の自分は子供だったけど今は成長したよ、とでも言ってるのでしょうか、サタミシュウのSM青春小説みたいですね。
でも、著者は自身が反映されたゼヴェリーンの肉欲を超えた”超官能”の世界を”精神疾患”と考えていたのでしょうかねぇ、解りません。
判らないことはもう一つ、
ワンダとの経験を経て、分別のある人間になったと自認するゼヴェリーンは今、女性に鞭で引っ叩かれる側から、女性を引っ叩く側の考えに替わっているのです。
女とは男の敵。女は男の奴隷であるか、女王として男を支配するか、そのどちらか。
男と女は同等の権利を持てない限り伴侶にはなり得ない。
男女の関係は金槌になるか金床になるかしかなく、女に鞭打たれることを望んだ自分は頓馬だった、と考えるようになったようです。
人の心は加虐性と被虐性の両方を要素を持っていて、どちらの要素が強めにあるによって対外的に求めるものが違ってくると普通に(普通か?)聞かされる話ですけど、ゼヴェリーンはSな人になってしまったのでしょうか。
そんなふうに移ろえるものなのでしょうか。
でも倒錯的、官能的快楽を得たくて使用人の女性を鞭打ってるようには見えず、完全に女性を敵視してるように感じます。
もう絶対にそっち側になんか行くものかという必死の思いもあるのでしょうか。
どう解釈したものか保留します。
この先色々なものを見聞きすれば、”とりあえずの解釈”くらいには辿り着けるかもしれません。
著者ザッヘル・フォン・マゾッホとはどんな人?
レオポルド・リッター・フォン・ザッヘル・マゾッホは1836年、当時はオーストリア帝国領のレンベルクという地で誕生しました。
現在ではウクライナ領でリヴィウというそうです。
父は警察署長、祖父はお医者さんで医学者、母は名家マゾッホ家の出身と「毛皮を着たヴィーナス」の著者は貴族なのですね。
ギムナジウムに進学する8歳のとき、少年マゾッホに生涯に渡り宿る、マゾヒズムな性癖を決定づける出来事が起きるのですが、それは後ほど。
父の度々の転勤に伴いプラハ、グラーツと移り、その間に大学生になり法律や歴史を学びます。
18歳で博士号を取得、オーストリアと他地域の近代史の講師と著述家としての仕事を始めます。
30歳のとき「コロメアのドン・ファン」という小説を発表して世間の注目を集めます。
こうして注目の作家として目されるようになったマゾッホは、ほぼ同時進行的に複数の女性たちとの交際を経て、その経験を元に「毛皮を着たヴィーナス」の執筆を開始するのは33歳のとき。
翌1870年「毛皮を着たヴィーナス」を発表し、作家業を専業するため大学講師の職を辞任するのでした。
この後の30代半ばから50代にかけて様々な女性たちと、婚約破棄、結婚、離婚、再婚を経て1895年に死去します。
享年59歳。
8歳、マゾヒズムの目覚め

17世紀初頭 メトロポリタン美術館
マゾッホは1888年に発表された手記で、幼少期に毛皮を纏う妖艶な美女に鞭で打擲され享楽を感じた体験を綴っているみたいです。
その手記によると、10歳頃(ん、8歳じゃないの?)父親の遠縁の女性 ”義理のおば”と呼ばれるゼノビア伯爵夫人(仮称のようです)に悶々とした恋心を抱いていたそうです。
ある日曜日の午後、伯爵夫人の子どもたちと遊ぼうと会いに行き、子供たちだけで過ごしていた折、黒豹の毛皮の外套を纏って現れた夫人は少年マゾッホにキスをくれたたそうです。
ついで夫人はマゾッホを寝室へ連れて行き、着替えを手伝わせたそうです。
夫人の前にひざまづき部屋履きを履かせたとき、自分の手の中で夫人の足が動くのを感じた少年は我を忘れ、その足にキスをしてしまったそうです。
その後、子供たちと屋敷内でかくれんぼを始めたとき、夫人の部屋の衣装掛けの後ろに隠れて数分後、夫人が若く麗しい男を連れて部屋にやってきてしまうのでした。
官能的な状況のところへ、今度は夫人の夫が友人を連れて部屋に現れたそうです。
怒りと戸惑いでどうすることも出来ずにいる夫に対しその刹那、夫人は電光石火のごとく、無言で夫の顔面に一撃を喰らわせ!、更に鞭を手にしてその場に居る男どもを部屋から退散させてしまったそうです。
悪いことに隠れていた衣装掛けが倒れてその様子を見ていたことがバレてしまい少年マゾッホは”密偵行為”のお仕置きとして、夫人に床に組み敷かれ激しく鞭打たれてしまったそうです。
恋心を抱いていた美女からの残酷な仕打ちに、涙を流し歯を食いしばり、痛みに身悶えながらも少年はそこはかとない劣情を感じてしまったそうです。
「毛皮を着たヴィーナス」でゼヴェリーンがワンダに語った「超官能」のきっかけは、この体験から来るのですね。
「毛皮を着たヴィーナス」への道
マゾッホの女性遍歴は小説「毛皮を着たヴィーナス」を生み出し、その作品世界を現実の世界で再現させた履歴でもあるようです。
1861年マゾッホ25歳のとき知り合った医師コトヴィッツ博士の妻アンナと不倫恋愛の末、駆け落ちするのですが、関係は4年で終わります。
亡命ポーランド人を自称する伯爵-その実、手癖の悪い薬屋の元徒弟の詐欺師の男にアンナを奪われてしまったのが理由です。
その後、高名な作家として世間に認識される1868年頃には、複数の女性たちとの、ほぼ同時進行的な交際を経て、バクダノフ男爵夫人を名乗る女優ファニー・ピストールと出会います。
ファニーの正体は実はただの作家志望者だったのですが、マゾッホは彼女とフィレンツェへ旅行して、そこで奴隷契約書を交わしたそうです。
このフィレンツェ旅行の年に「毛皮を着たヴィーナス」が執筆されます。
アンナとの関係を終わらせることになる自称”亡命ポーランド人”は「毛皮を着たヴィーナス」においては”ギリシャ人”の男の源泉になったみたいですね。
また、ファニーとの奴隷契約書は物語の中でゼヴェリーンがワンダと交わした契約書の内容、そのままだったとか。
複数の女優や女流作家との情交を含めて、全ての女性との性愛経験が、小説「毛皮を着たヴィーナス」とヒロイン ワンダを形作っているのですね。

ヒロイン ワンダ誕生
ワンダは虚構の人物ですが、「毛皮を着たヴィーナス」が発表された翌年、マゾッホは現実世界にワンダを誕生させてしまいます。
1871年、グラーツの貧民街のお針子アンゲリカ・アウローラ・リューメリンが偽名を名乗りマゾッホに接近し、二人は文通をはじめます。
この頃マゾッホは別の女性と婚約を交わしていましたがその婚約を破棄して1873年アンゲリカと結婚します。
アンゲリカを貴婦人に”調教”して、ワンダ・マゾッホを名乗らせてワンダと奴隷契約書を交わしたそうです。
ここに虚構の女王さまが現実に誕生しました。
ワンダへの”調教”は次の段階へ進みます。
新聞広告でワンダの愛人を募集したり、街中を男を漁る目的で歩かせたり、ワンダに自分の目の前で他の男と姦通をさせたりしたそうです。
最初こそ無理強いされての行為だったワンダでしたが、そのうち何かしらタガが外れてしまったのか自ら進んで男漁りをするようになってしまったそうです。
マゾッホは自身の思惑通りの女になってしまった妻の行為に嫉妬で狂わんばかりの心情になったようです。
この後、これもマゾッホ自身が描いた筋書きなのでしょうか、自分が主宰する文芸雑誌の編集権と一緒に”ギリシャ人”ならぬフランス人青年にワンダを奪われてしまいます。
当時マゾッホは有名作家の様ですから、何かと関わりたくて接触してくる人もいたのでしょうけど、そもそもアンゲリカはどんな目的でマゾッホに接近しのでしょうか。
パートナーに変態行為を強要されているうちに、自身が変態行為を楽しむ人になってしまうというAVのようなことってあるのでしょうか。
解りませんね。
もしかしたらアンゲリカもワンダと同様に、”変態調教”をされているうちに自身の性根の魔性に気付いてしまったのか、あるいはある時点からパートナーに対して諦めの心情を抱きながら日々を過ごしていたのでしょうか。