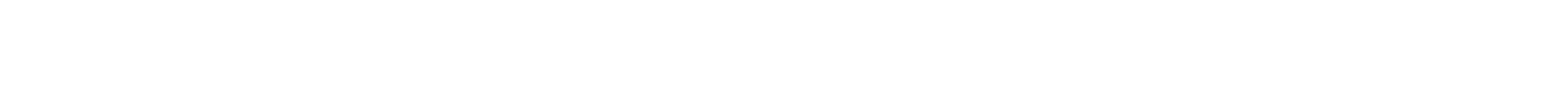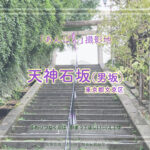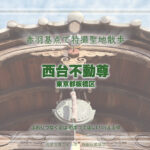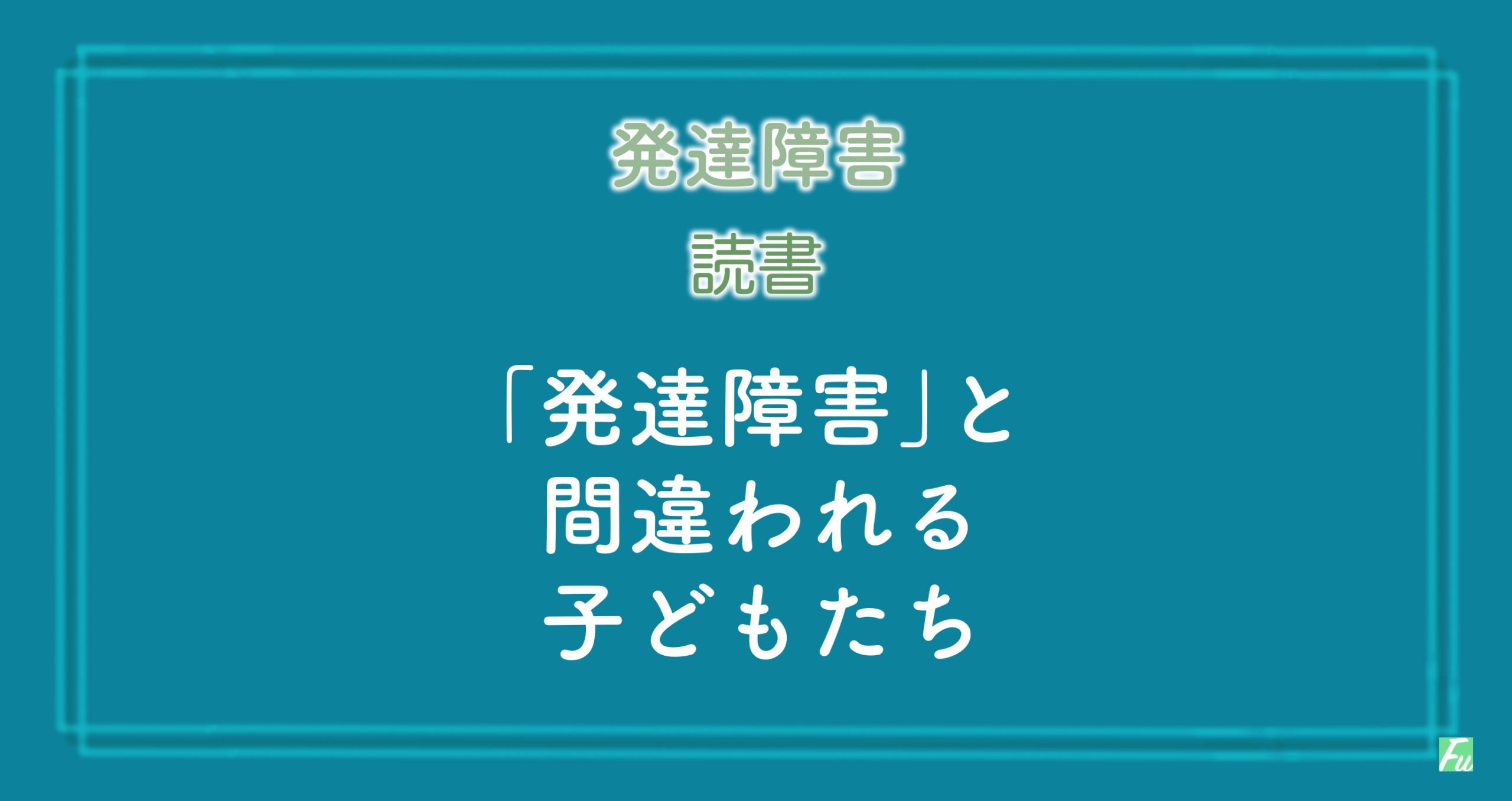
「発達障害」と間違われる子どもたち 成田奈緒子 著 青春出版社 青春新書
を読みました。
本屋さんで時々目にする発達障害グレーゾーン系の内容かなと思って読んでみたのですが、ちょっと違いました。
生活のリズムを整えて質の良い睡眠を摂ることが大切です、子どもは勿論ご両親も。
と語っている本でした。
「発達障害」って随分普通に耳にするようになった気がする。

自分の息子が発達障害と診断されたからでしょうけど、発達障害という言葉が、いつの間にか普通に世間で話されてる印象を感じていたのですが、あながち勘違いでもなかったようです。
この本で語られている話によれば、
2000年文科省が行った「特殊教育のあり方に関する会議」で通常学級に在籍する生徒の中に「特別の支援を必要とする児童生徒生徒の支援の必要性」という意見を受けて、その後何度かの全国実態調査が行われたそうです。
この調査で「発達障害の可能性」のある児童生徒の人数は調査を重ねる度に増加してゆくことになるそうです。
教育現場でもそれまで以上に意識されるようになったからでしょうね。
そうした中で「発達障害支援者法」が成立して、それまでにない支援が行われることになったそうです。
支援学級を設置する学校が増えていったそうです。
自分の息子 いゆ太くん(仮名)が小学三年生の時に知能検査の結果を経て支援学級に編入した時期も、この世間の動きの最中だったんだなとしみじみ思うのです。
”もどき”と脳と睡眠

この本の著者、成田奈緒子氏は脳科学の研究をしながら小児科医として発達障害が疑われる子供達を診療されている方だそうですね。
多くの子供達を診ていて、
「発達障害の診断がつかないのに、発達障害と見分けのつかない症候を示す」
子供が多かったのだそうです。
そのような「本当はどうなのかしら」という症候を著者はこの本で、「発達障害もどき」という独自の造語で語ってます。
”もどき”だなんてバッサリ切り捨てるような言い方ですが、本の内容は誰も切り捨ててません。
著者は診察に訪れる子供の親に普段の生活状況をリサーチするそうです。
発達障害と見分けのつかない症候を示す子供は、親の生活サイクルと合わせるように、
夜更かしになりがちで、あまり睡眠をとっていないケースが多いそうで、それが脳の正常な発育を妨げているのだとか。
睡眠時間をきちんと摂る生活サイクルに改めてみたところ、発達障害のような症候が消えていった例が多いとのことです。

睡眠時間が短ければ、大人だって心身共に思ったように動けませんよね。
子供は身体と同様に脳も発達途上なのでしょう。
親の乱れた生活リズムに合わせれば、心身共に正常に機能しないのでしょうね。
まぁ忙しい現代人は望んでリズムの乱れた状況になってるわけではないですよね。
我が家もそうです。
質の良い睡眠を摂り、早朝に太陽の光を浴びる。
生活のリズムを整えることで、発達障害を疑うような振る舞いが自然と無くなっていくのであれば、これほど良い事はありませんね。
これは親が主導しなければ出来ないことでしょうから、家族のみんなの生活リズムも整うのであれば家族全員にとっても良い事でしょう。
生活のリズムを整えても子供の様子が変わらない様であれば、その時点で発達障害を疑ってみては?、と語られてますね。
専門家や研究者ではない私が本を一冊読んだくらいで訳知り顔で記事を書くつもりはないのですが、発達障害の事でこの本は”参考なる知識”として読んでおくのもいいのかなと、感じた一冊でした。
一方で私は自分と家族のあの頃を振り替える心境になりました。
息子の発達障害を疑ったあの頃、こういう話はすでに一般的だったのかな?。
発達障害と診断された前後の色々な検査等にどのような人たちが関わっていたのかな?。
当時も知ろうとは、考えも及びませんでしたから、今となっては当然分かりません。
また、当時の私たち家族の生活環境や生活リズムはどうだったのだろうか。
私の息子は2023年春、障害者として社会人デビューしました。
今更ですね・・・。
本のタイトル
タイトル
「発達障害」と間違われる子どもたち
著者 成田奈緒子
2023年 青春出版社 青春新書 刊