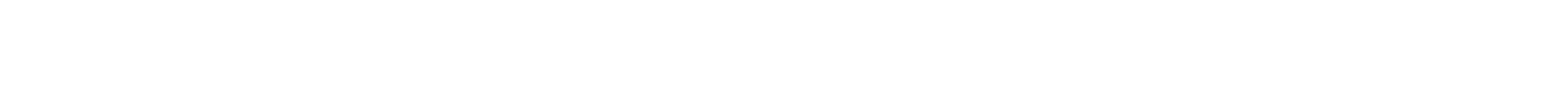ゴッホについて知りたくなって、いく冊かのゴッホ本を手にしてみたら、新たに関心を惹起させる人物がふたり・・・3人かな、登場するのでした。
お一人目は、ゴッホコレクションでは世界2位と言われるクレラー=ミュラー美術館を設立したある裕福な企業家妻です。
お二人目は日本人です。

- クレラー=ミュラー美術館所蔵作品の画像はパブリックドメインではない為、当記事では他の美術館の画像を添えております。(使用画像はパブリックドメイン、CC0です。)
ゴッホを爆買いした裕福な企業家妻の想いとは

その企業家妻は、41歳のとき大病を患い、手術に成功して退院出来たら、自身の絵画コレクションを増やして公共の美術館を設立しようと決意したそうです。
手術は成功して翌年、大量のゴッホ作品をオークションで落札して、いよいよ美術館設立に動き出します。
へレーネ・クレラー=ミュラーは1869年ドイツのホルストという村で生まれます。
因みにこの年は、ゴッホは16歳。美術商グーピル商会のハーグ支店に就職します。
へレーネの父ウィルヘルムは製鉄会社で取締役にまで昇進した後、義兄と共に鉄鉱石や石炭を扱う「Wm.h.ミュラー社」を起業して成功を収めたそうで、ミュラー家は裕福な家庭の様ですね。
1888年19歳のとき、父親の会社で能力を認められて経営陣に加わった、7歳年上のアントン・クレラーと結婚します。
翌年二人の恋愛と結婚をアシストした父親ウィルヘルムが亡くなり、アントンは義父で創業者の会社の経営を引き継ぎ、会社を国際企業としてさらに成長させたそうです。
1905年、当時オランダで人気の美術講師ブレマーの講義を長女と共に受講したのが芸術に関心を持つきっかけとなったのでしょうか、ブレマーを専属顧問に雇い、絵画の購入をはじめます。
1908年にゴッホの作品を初購入します。
夫が経営する会社は業績好調でミュラー家の資産は膨らむ一方です。
夫の財力で絵画を買い漁ることはブルジョワの奥さまにとっては普通のことみたいですね。
その資産で、1912年(手術に成功して退院した年ですね)にはパリやアムステルダムのオークションで32点のゴッホ作品を落札します。この年の4月だけで15点も購入したそうですよ。
最高傑作と言われる「夜のプロヴァンスの田舎道」「アルルの跳ね橋」が含まれてます。
この爆買いがきっかけとなって画商たちはゴッホ作品に注目する様になり、評価額もかなり上昇した様です。
という事は、へレーネはゴッホが芸術史に名を残す偉大な画家となる立役者ということになるのですかねぇ。
森の中の邸宅付きの広大な土地を購入して、いよいよ美術館の設立に動き出そうとしますが
中々上手く事が運ばず、ようやく建物の建築にかかろうとする頃、夫の会社は業績悪化により計画は中断してしまうそうです。
計画中止から5年が経った頃、会社の経営状態が上向きだすと財団を設立して絵画コレクションを財団保有にします。
続いてクレラー・ミュラー家所有の土地を公共公園財団に、絵画コレクションを政府に譲渡して官民一体のプロジェクトとして美術館設立へ再度動き出します。
こうして1938年7月、クレラー・ミュラー美術館がオープン。へレーネが初代館長に就任するのです、この時69歳。
1年半後70歳で亡くなります。

すごく興味深い人物ですが正直なところ、へレーネが美術館設立に情熱を傾けるくらいにゴッホ愛に目覚めた実際の理由をよく分からないです。
へレーネは一度始めた事は情熱を持ってとことん取り組まないと気が済まない頑張り屋さんだったみたいですね。
それでいて、自身の生きてきた時代の世間や周囲の価値観に迎合できず違和感を感じて日々を過ごしてきたそうです。
だけど生まれた時から経済的に困る事なく生きてきた女性が、貧困と孤独の中で生きて、描いてきた画家の作品の何にシンパシーを感じたのでしょうね。
ゴッホが亡くなって、そんなに時が経過していない頃から、かなりのゴッホ推しだったお抱えの美術講師ブレマーに感化されたのでしょうか。
それでも美術館設立の夢が中断になった時にはショックからなのでしょうか、神経症になってしまうくらいですから、単なる金持ちの道楽行為とは言い切れない様に思えます。
へレーネは自身の生きた時代の価値観に馴染なかったからなのか、友人も多くはなかった様で、経済的には豊かであっても何かしらの孤独を抱えていて(令嬢にしばしばありがち?)、読書家でもある彼女は書物から得た偉人たちの言葉に気持ちを委ねて青春時代を過ごしていたそうです。
そうして育まれた感性はゴッホの絵に仮託したくなる何かを感じたのでしょうか。
ゴッホが死後に評価された、というのは誤りで、自死に繋がる行為を行う少し前辺りから世間の見る目がちょっとずつ変わってきたようです。(へレーネがゴッホ作品を買いまくるまで爆発的に、もしくは安定的に注目されるほどではなかったみたいですが)
ゴッホ自身もその事は認識していたらしくて、自死を選んだ理由もはっきりしないと言われてます。
もしゴッホが亡くなることがなければ、へレーネと邂逅することもあったでしょうかね、そうなった時それぞれが抱える孤独感も交感され、報われる事になったのでしょうか。
でも、こういう空想は単純すぎますね、
ゴッホが亡くなるのが実際の出来事よりもずっと後のことだったとするならば、ゴッホを取り巻く全ての事象が実際とは異なってしまうでしょうしね。
へレーネがゴッホ作品を大量購入した1912年、ゴッホが生きていたらその年58歳です。

それとゴッホの絵を大切に守り続けてきた女性がもう一人いますから。
ゴッホの弟テオはゴッホの死の半年後に後を追う様に亡くなります。
テオの妻ヨーは夫の死後、義兄の絵画200点余りを管理し決して売却することなく守り続けたそうです。
その膨大な作品たちは息子フィンセントに相続され、アムステルダムのゴッホ美術館に収蔵されてます。
「たゆたえども沈まず」ゴッホ兄弟の傍らの日本人

今更ですけど原田マハ氏の小説を初めて読みました、素敵な物語ですね、「たゆたえども沈まず」
フィンセントとテオドロス、”互いを自身の半身”と想うゴッホ兄弟の絆と、そんな兄弟を見守る二人の日本人のお話ですね。
物語のお仕舞いが近付いてくると、1ページ読み終えるのも苦労するくらいに涙腺が緩み続けます。
ゴッホ兄弟の兄フィンセントは生真面目だけどムラのある、人付き合いの上手でない難しい性格の人なのかと想像してしまいます。
そんな性格が故に、不器用な生き方しか出来ず、何をしても長続きしなくて、回り道して、空回りして、誰かを思って行動したことが残念な結果になってしまう。
画家になると決意してからも、あらゆる事、やる事なす事上手く行かず、常に孤独と闘う人生の様に見えてしまい、知る程にほんの少しだけ身につまされる気分になってしまいそうです。
そんな兄を支える事ができるのは自分しかいないという思いから支援を続ける弟テオドルス。
兄の絵に衝撃を感じて、将来必ず世間が認めてくれる日が来ると信じて、支え続けていこうと決めたものの、兄を思うが故に反発したり不安や葛藤に苛まれる弟。
恋心を抱いた幼なじみと再会して結婚して幸せの絶頂にいる時でさえ、兄から送られてくる絵から伝わってくる孤独と闘っている兄を思えば、自分だけ幸せになっていいのかと自問するテオドルスが痛々しいです。
ゴッホ兄弟と出逢って見守る二人の日本人。
ゴッホはまるで理想の女性を想うように日本に憧れ、「自分だけの日本」を求めてパリからアルルへ行くのですが、この「自分だけの日本」の意味が最初はよく分からなかったのです。
ゴッホが日本を強く意識し始めたのは、浮世絵がきっかけなのでしょうかね。
19世紀末欧州は日本ブームでゴッホはパリ滞在の二年間に多くの浮世絵に触れる機会があったみたいですね。
日本に渡航した事は無く、日本人と邂逅した記録もないゴッホが日本を知るきっかけは浮世絵と書物からでしょうね。
それらを通じて自身のアイデンティティと絡めた日本と日本人を想像し、”架空の妄想日本”という理想郷に恋焦がれたのでしょうか。
そんな”妄想日本”を南仏アルルの地に重ねていたのでしょうか。
アルルで築こうとした”芸術家の理想郷”というのも”妄想日本”のイメージからの着想だったということなのだとか。
実際にアルル行きを薦めたのは、モンマルトルで同じ画塾の同窓になったロートレックだそうですが、小説では日本人の林忠正なのですね。
林忠正はパリで浮世絵を販売する画商で、ゴッホ兄弟がパリに居た期間とも重なっていた実在の人物です。
ただゴッホ兄弟と邂逅した記録はないのだそうです。
でも実際の出来事に架空の出来事を絡めるのが小説なのですから、日本に恋する男の人生を、次のステージへ誘うのが日本人だなんてファンタジーですね。
林は物事を見通す鋭利な刃物のような男で、発言が予言のように状況に符号する人物として書かれてます。
この小説をファンタジーと解釈するならば、
時に厳かに、けれどもテオと同じく、フィンセントの可能性を信じて見守り続ける実在感を伴う「導きの精霊」の様にも想像します。
もう一人、日本人が登場します。
加納重吉は学生時代に3年先輩の林と出会い林の導きでパリへやって来て林の元で働きます。
人の良いシゲさんはテオと出会い、パリにおいては異国人同士ということもあってか、掛け替えのない友達になります。
身近にテオを見つめることの出来るシゲさんは旧加賀藩、石川県から官費生として開成学校に入学した、代々高名な蘭学者の家に生まれた秀才で・・・実在しない人物です。
ひょっとして、人として愛らしいけど、実在しないシゲさんは、林の隠し持つもう一つの人格が表層化した存在なのかなぁと思ったりします。
二人でひとつのツンデレ日本人風精霊(ツンが林で、デレがシゲさんか)が、”互いを自身の半身”と思うゴッホ兄弟をすぐ傍らから見守ることで読者も間近にゴッホ兄弟の人生を目撃できるのですね。
この小説の登場人物の殆どに愛しさを感じるます、特にシゲさんに。
この物語ではフィンセントは孤独じゃなかったと思いたいです。
現実の世界でもフィンセント・ファン・ゴッホは一人じゃなかった。この人を信じて見守っていた人は、多くはなかったかもしれないけど確かにいたでしょう。
時空を越えてシンパシーを感じる人々が世界中に現れ、へレーネだってそんな一人ですよね。
そう考えるとフィンセントが自死を選択してしまう心境になってしまうことに、何となく悔しさの様なものを感じてしまいます。

弟夫婦に経済的負担を掛けていたことに自責の念に囚われてのことだと言われてますね。
経済的負担は本当のことの様ですが、テオとヨーはこんなこと望むわけなどないのに。
愛すべき弟とその家族を思っての行為であるならば痛々しくて切な過ぎます。