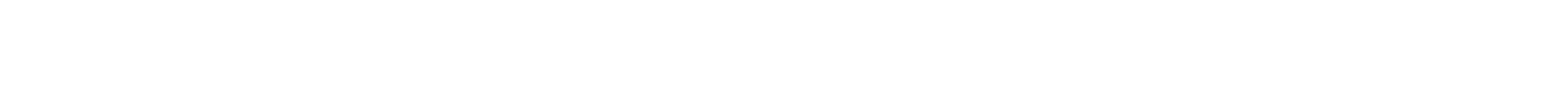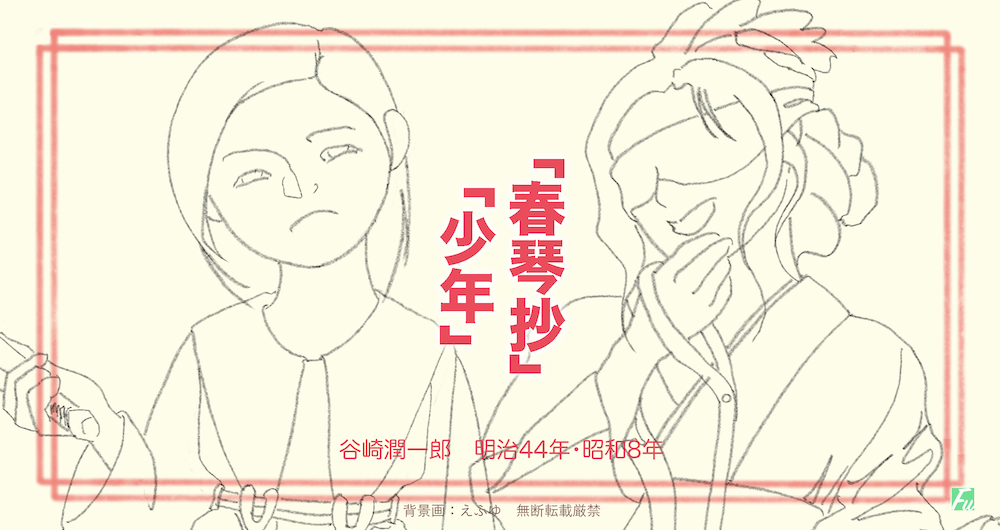
谷崎潤一郎の「春琴抄」に触れたら、同じく谷崎の短編「少年」をまた読んでみたくなりました。
イメージ画:えふゆ 無断転載厳禁
目次
「春琴抄」は、ある男の人生 ”インナースペース”?

この物語は、師弟の契りを結んだ ある男女に関心を持った作家によるルポルタージュという体裁で語られている感じですかね。
「春琴抄」は盲目の琴の女師匠でサディスティックな春琴に、ほぼ一生を捧げた男 佐助の物語です。
どんなに酷い扱いを受けても愛と喜びを持って尽くしたいわば「被虐一代男」とでも言えばいいでしょうか。
ラノベの風味?
触れ合った始まりは二人が少年と少女のとき、丁稚とお嬢様という身の上。
盲目となってしまったお嬢様を、琴のお師匠の元に手を繋いでお供をすることになった丁稚の少年。
恋愛感情など、自覚できないくらい朧げな少年の思いを、盲目だからこそ感じられたかも知れない少女、身の上の違いもあって言葉さえろくに交わす事なく、それ以上交わることのなかった幼い二人。
この時点では、相互に愛情もある様な無いような、可愛いらしさ、微笑ましさみたいなものを感じます。
琴を通じてこれまでに無く近しくなる二人は師弟関係となるのですが、加虐性の強い春琴は佐助を理不尽で残虐に扱います。
その様は、春琴を自分たちの子の誰よりも可愛がり、我儘娘に育てた両親さえ引いてしまうくらいの振る舞いです。
春琴に虐げられる事は佐助にとっては堪らなく望んだ状況の様です。
春琴は元々サディスティックな性格に育ったとしても佐助の望む事を意識的に行っていたのでしょうか?
だとすれば、佐助と春琴の間には周囲の人に気付けない、そして理解出来ない関係を育んでいたのかもしれないですね。
ただ、この辺りなど 日常系のコミックやアニメにありそうな(あくまでイメージ)、気の強い積極的な女子に振り回され、困っちゃうけど離れられない男の子的なものをそこはかとなく感じたりもします。
でも可愛いらしさ、微笑ましさも、ある年齢に達しても変化がなければ滑稽に映る場合だってある気がしますけど。
被虐男の企み?
こんな風にも考えます。
もしかしたら春琴は、佐助以外の「男」を知らないのかもしれない。
そうであるならば佐助とって、春琴を自分の望む様に振る舞ってくれる女に「調教」するのは容易いことだったのかもしれないです。
そういった日々の果てに、春琴を襲う不幸があって、佐助のとった行動は、
二人の交歓を更なる深みへと埋没させていく様です。
この猟奇的行動も佐助の企みの ”仕上げ” なのではと勘繰ってしまいそうです、自らの身体を傷つけてまで。
だから、「ある意味これも美しい愛の物語」の様に思わせておいて、
佐助の被虐の愛による、利己的で自己完結の内向きの世界でしかなかった様にも思えます。

佐助のとった最後の行いは、自分で拵えた”檻”に春琴を閉じ込めさせる為だったのか?
閉じ込められた春琴はそんな佐助の望んだ通りに振る舞わざるを得なかったのかな、?
春琴自身は自覚していようが、そうでなかろうが、・・・・とさえ思えてしまいます。
「少年」お屋敷は異世界の魔窟

主人公の少年 "栄ちゃん"はある時、学校では評判の意気地なしで弱虫のお坊ちゃん 信一に自宅に遊びに来る様に誘われます。
信一の家は資産持ちです。
洋館も建てられている厳しい門のあるお屋敷を訪ねると、学校では餓鬼大将の仙吉が信一のご機嫌を取っていて、信一は姉の光子と仙吉に対して王様の様に振る舞ってます。
信一の言い出す様々な”ごっこ”を一緒に遊ぶうちに"栄ちゃん"も自然と信一の家来の様になっていきます。
同じ面子でありながら、学校での現実と異なる人間関係を過ごす少年少女たちには被虐・加虐の意識がないまま行為はエスカレートしていきます。
かなり悪魔的な物語

「少年」を改めて読んでみると谷崎が紡ぐ美と被虐の全てが凝縮されている様な気持ちになります。
文章が、言葉選びがとても官能的で、かなり悪魔的な物語でした。
「少年」が発表されたのが1911年(明治44年)谷崎潤一郎 25歳のときです。
この年に、この「少年」が永井荷風に激賛されて文壇デビューとなったそうです。
関西に移り、38歳に時に発表した「痴人の愛」より表現にリミッターが掛かってないのも当然というか自然なことでしょうか。
少年少女の無邪気な暴走のお話は、永井荷風が評したように、年齢を重ねてしまうと書けるものではないのでしょうね。
ちなみに「春琴抄」が発表されるのは1933年(昭和8年)、谷崎47歳の年です。
女王の国

信一坊ちゃんのお屋敷で行われる”ごっこ”遊びのシチュエーションは様々です。
ごっこの舞台は、”異世界感”を催させ、演じている自分たちを”別人”に変えてしまうのでしょうね。
そのうちに、心の内や身振りの全てが、「ごっこの別人」と同化して、加虐も被虐も、現実も、非現実も境界が曖昧になってしまうのでしょうか。
少年少女たちは性も何もかも無自覚のまま、単なるイタズラを繰り返しているくらいにしか思ってないのでしょうね。
そこに微かな甘美を感じる一瞬を徐々に自覚するようになってしまうのでしょうか・・・。
その行き着く先は?
大人になった 栄ちゃんの一人称で物語は語られてます。
四人しか居ない小さなの国を支配する女王(光子)の無慈悲な命令を、新しい遊びを与えられたが如く嬉々として従う様になってしまう三人の少年。
「微かな甘美」は肥大化して被虐と言う喜びに囚われてしまったのでしょうか。
その三頭の”奴隷”が、さらに光子を女王たらしめるのでしょうか。
そういえば、ヒロインの名前は「卍」のヒロインと同じで 光子 なのですね。
同じ作家の小説でも関連がないことは承知してますけど、「卍」の光子はどんな幼少期を過ごしたのでしょうね?。
「少年」はなんだか懐かしさを内包してる?
好奇心はあっても性的嗜好どころか、自身の性別さえあまり意識してなさそうな少年少女の頃に、こういったシチュエーションってなんだかありがちな気分になって来ました。
懐かしさとでもいうのでしょうか、
この物語の様な過激さはないけれど、小学生の頃には、この雰囲気に近い状況を経験した事ってありませんか?。
普段は男の子たちだけで遊んでいて、”ごっこ遊び”なんかもしていた・・・様な朧げな記憶。
そこに時々女の子が混ざっていたりした事。
何かしらの禁断の扉を開ける萌芽など生まれませんが、ちょっとだけ”むずっ”とした気持ちになった事。
全ては性を意識してないが故の事ではあったけど、遊びの内容によっては「谷崎世界」のような扉を開けてしまっていたのかな・・・。
「少年」で”谷崎免疫”を定着させる?

個人的に谷崎潤一郎の作品で初めて読んだ作品がこの「少年」でした。
谷崎潤一郎がどんな作家なのかよく知らないで読んだ為、衝撃は半端ではなくて、
理解できない、覗いてはいけない世界を知ってしまったかの様な気持ち悪さから、もうこの作家の小説を読むことはないだろうと思ったものでした。
それなのにその後「痴人の愛」を読んでみたのは何故なのか覚えてないなぁ・・・。
「少年」を改めて読むと、初めて読んだ時のインパクトは薄れてるものの、何かしらの”より、濃い”ものが薄れることはないなぁと感じてしまいます。
でも自分の場合は、始まりが「少年」だったことでその後読んだ谷崎作品が比較的自然に受け入れられている気がするのです。
その後、これまで読んだ他の谷崎作品が比較的マイルドに感じられてます。
大人はある程度の理性を働かせ逡巡もするでしょうけど、「少年」には理性がまだ乏しく、幼いからこそのためらいのない残虐性があるのでしょうか。
自分は谷崎作品を全て読んでないです。
これからも読破するつもりもないですが、気になったときに気になる物語を手にするでしょうね。
自分は少し”谷崎慣れ”したつもりでいるかもしれませんが、
これから出逢う谷崎作品で「セカンドインパクト」はあるのでしょうかね。
恐れ慄くことにならないといいなと思ってます。